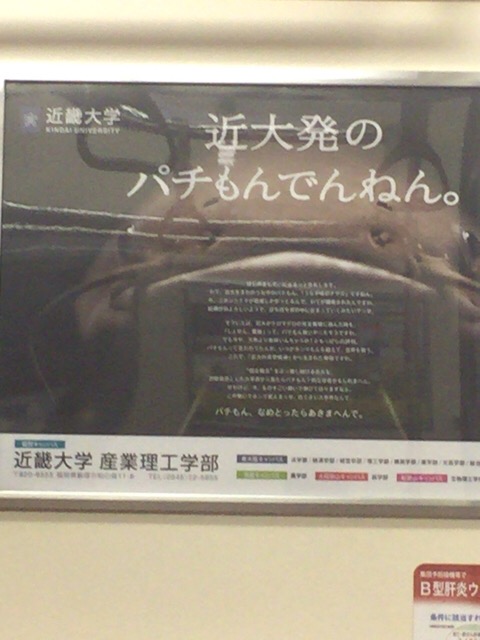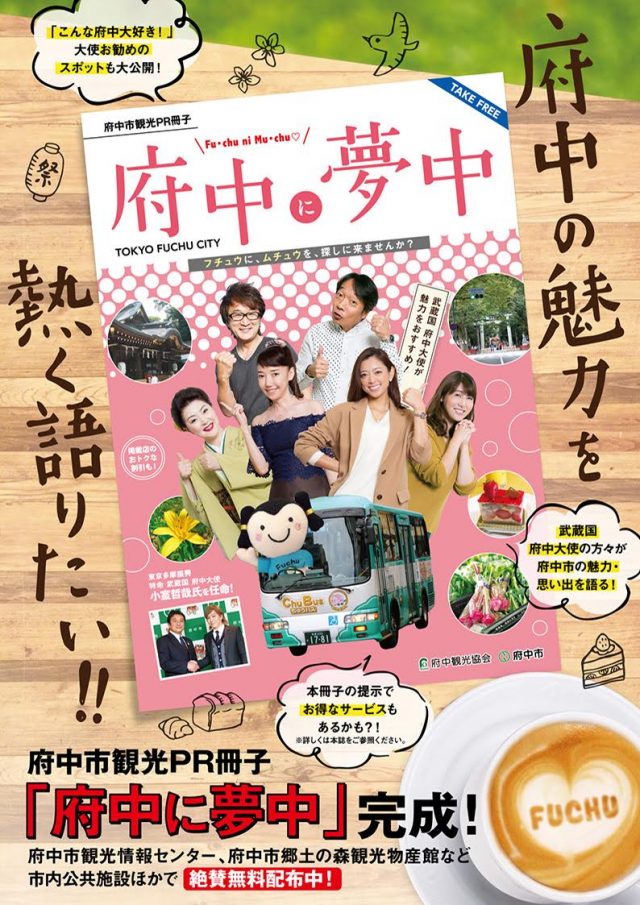2025年問題というのをご存知でしょうか?
国民の1/3が65歳以上、1/5が75歳以上という未知の時代に入ります。
それは、団塊の世代が75歳以上に入り、そこをアテにしていた各業界の消費が落ちていく時代に入ります。
旅行業というのは平和産業で、かつ余暇産業です。
つまりは平和でかつ、余裕がないと家庭内予算はどうしても削られ、売上が上がりません。
今後、AIの導入も更に増えていくでしょう。
その昔手塚治虫の漫画で、パソコンに向かって、今夜のレシピは?なんていうだけでレシピが出される、そんな冷蔵庫も発売されたくらいです。
いっそのことパソコンに、北海道の自然を見に行きたい、レンタカーで行きたい、安く行きたい
こんなことをいうとパソコン上に、あなたのおすすめは・・・なんてパソコンがしゃべるそんな時代になるのだろうなと思います。
そうすると、旅行業のカウンターは軒並み潰れます。
今のカウンター従事者もそうですが、今やお客様の方が情報を持っていたりしますので、お客様からすると物足りないわけです。
また人口が少なくなるのだから、こんどはOTA(オンライントラベルエージェント)だってつぶれるかM&Aされていきます。
その中で、鉄道系の旅行会社は生き残っていくだろうなと思います。
それでも今のままではだめです。
勝手気ままに予想します。
今後旅行会社のカウンターは旅行予約をする場所だけじゃなくなっていく。
これに尽きるのではないかと思います。
今WEBを検索しても今の若い子は、北海道に行きたいけどそこで何が体験できるのか、どんな絶景が見えるのか
どんなフォトジェニックなものがあるのか、
どうやらどうやってそういう情報を入手したらいいか、わからないそうです。
いわゆる検索の迷い子ってやつで、もはやどうやって検索すればいいのかさえ、わからない人が増えています。
旅先に行っても、何したらいいのかわからなく時間を持て余す→旅はつまらない
こういう方程式になってしまうわけです。
これでは旅行業は未来がなく、斜陽産業になってしまいます。
これから日本は人口が減る時代が来るのですから、外国人観光客をたくさん受け入れ、消費を彼らに頼るしかありません。
つまり、観光立国になるしか今のところ道はないのです。だから斜陽産業になるわけにはいかないのです。
もっと未来をつくるには、若い子たちが積極的に旅行に出かけるようにならないといけません。
だからいっそ
旅行のカウンターでそういう情報を得られる、インフォメーションセンターになってしまえばいい。
そう私は考えます。
旅行のカウンターは予約だけするのには、とてもスペースがもったいない。
暇な旅行屋さんのカウンター見ても、従業員がくっちゃべっています。大手でも同じです。
もうひとつは、
旅先の体験ものを旅行カウンターで体験フェアみたいなのができればいい。
これは観光地から補助金などを得て運営すればいい。
さらには、外国人観光客のインフォメーションセンターになればいい。
そして外国人がそのまま旅行を予約できるような流れにならなきゃだめですね。
しかもいまのところこれも補助金を狙える。
こうすることで、地元に根付いたトラベルワンダーランド(これはHISの言い方ですが)のようになっていけばいいと思います。
旅行に関する遊び場、旅行の相談場所みたいなイメージです。
営業をしていて思いますが、「売ろう売ろう」とすると、ものって余計に売れません。
例えば、アパレルショップで、後ろから話しかけると買うのやめてしまうみたいな感覚です。
そういう意味で旅行会社のカウンターは、旅先の情報まで知るコンシェルジュになっていく、そんな未来予測をしています。
会社は永遠に続かなければなりません。
また成長し続ける会社はありません。
どこかで成長は一度は止まります。
こんな未来予測の元、緩やかに方向転換していく時期がどの業種も訪れると思います。
私たちも負けじと、緩やかに方向転換し、クリエイティブで観光を元気に、をモットーに
もっと深く旅行・観光分野を学んでくらいついていこうと思います。
私自身旅行業に9年勤め、今も旅行・観光へのお役立ちとして、会社を経営しています。
当然、旅行・観光業界が盛り上がらないと我々もお仕事がないわけです。
必ず観光立国になれると信じています。